CATEYE(キャットアイ)の自転車ライトを使っている人は多いのではないだろうか。
私もその一人だ。
小学校の頃、初めてGIANTのマウンテンバイクを親に買ってもらったときも、キャットアイの自転車ライトを使っていた。
そして、社会人になり、オッサンなった今も、キャットアイの自転車ライトを使っている。
そんな中、初めてキャットアイの自転車ライトが故障で点灯しなくなった。
Webで同様の症状が無いかを徘徊していると、どうやら3年くらいで点灯しなくなる故障は多いようだ。
という訳で、キャットアイの自転車ライトを分解して、故障修理できたので、その模様をレポートしたいと思う。
私のキャットアイ LEDライトは、HL-EL140だが、HL-EL130、HL-EL135、HL-EL145も同じ形のライトなので、同様にして故障修理ができると思う。
キャットアイの自転車ライトの分解
まずは、電池を取り外す。
そして、このLEDライト部の透明なカバーをがんばって外す。

この透明部分のカバーを外すのがけっこう難しい。
コツは、透明のカバー部分を下記のように捻って隙間を作ることだ。
できた隙間に、マイナスドライバーなどを入れて、ギコギコとテコの原理で少しずつ外していくと良い。
両サイドにツメがあり、この爪が外れると、スポッと外すことができる。

こんな感じだ。
ツメを外すことができれば、LEDの照射方向に向けて、透明カバーは外れる。

これが、LEDに電力を供給し、また「点灯/点滅」を制御するための回路だ。
よく見ると、浸水したような後がある。
ちなみに、このLEDライトは、構造をよく見てみると分かるが、防水に対応していない。
防水に対応していないが、進行方向に対して水平に設置すると、雨水がボディー部に入らないように工夫されているが、下記図のように電池2つが重なるように横に立ててしまうと、穴から浸水してしまうようだ。
この浸水が原因で、ハンダ部分が劣化して、接触不良を起こしていたようだ。
また、電池端子と下記回路を接続するVSS/VCCと書いた端子も錆びている可能性があるので、ここも接点復活剤などをスプレーして、磨いておくと良さそうだ。
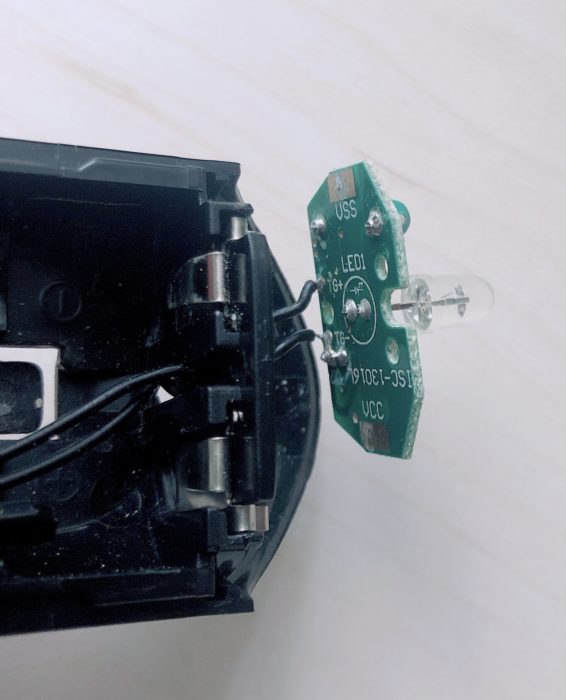
再ハンダをすれば直りそうだということが分かったので、基板にハンダをしやすいように、ケーブル処理を行う。
LEDが載った基板と、電池のお尻側のスイッチとの間は、2本のケーブルで接続されており、このケーブルの長さが短く、LED基板が自由に動かないようになっている。
ケーブルにゆとりをもたせて、LED基板を可動できるようにするために、お尻側のスイッチ基板を外す。

お尻側(スイッチ側)の基板を外せば、こんなふうにケーブルにゆとりをもたせることができるようになる。

LED基板が自由に動くようになったら、ハンダ不良箇所をよく確認する。
このケーブルを基板に留めている部分に若干浸水したようで、ハンダが錆びというか侵食されている感じがあった。
なので、ここのハンダを溶かして、再度ハンダ付けする。
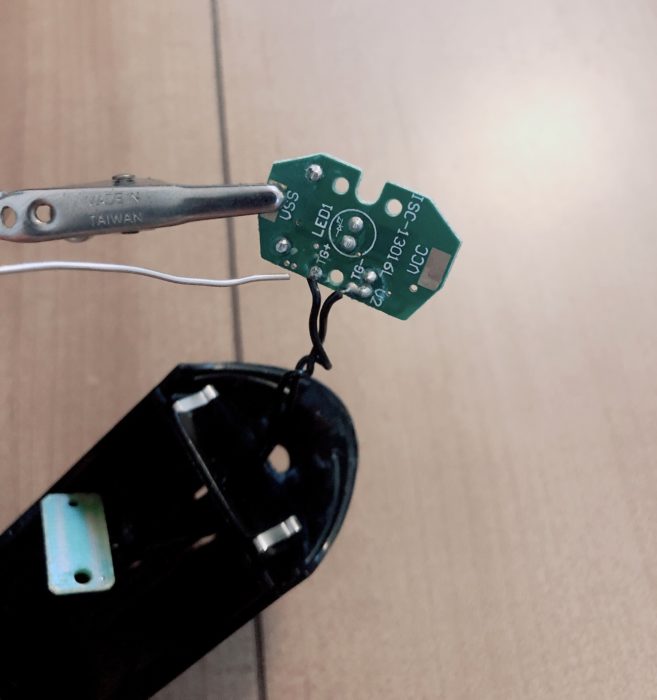
LEDが付いている方の基板面も一応チェックしておく。
こっちは問題なさそう。
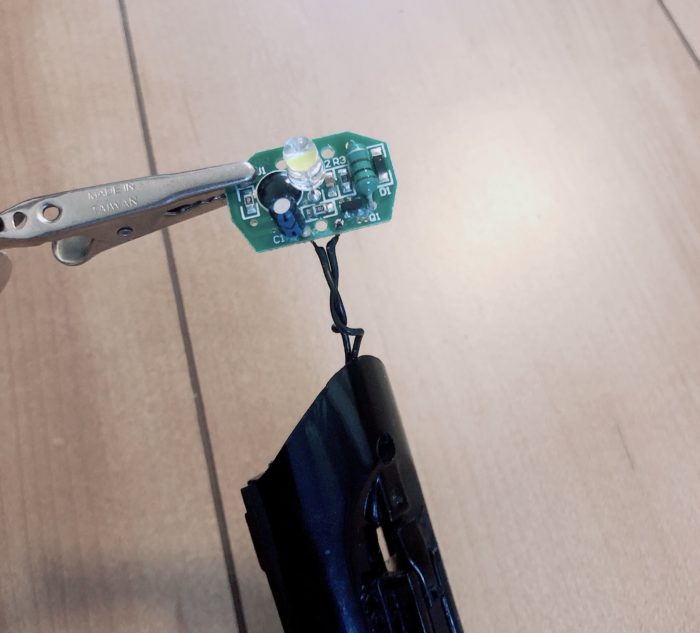
さて、分解していた基板を元に戻して、電池をはめて、いざスイッチON!
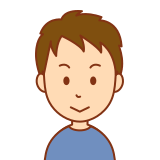
たのむ!点灯してくれ!!
さて、結果は!?

ピカーー!!!
嬉しい。見事に故障修理により、復活させることができた。
もう二度と浸水しないように、セロファンテープやホットボンドで、穴という穴を埋めておいた。
これで再度故障することは無いと信じたい。
1500円も出せば変えるキャットアイの自転車ライトを、わざわざハンダゴテまで出動させて故障修理するか!?という話もあると思うが、直せるものはぜひ直して長く使って欲しいと思う。
自分で修理した機器は、その後の愛着も増しますし。



コメント